|
9/27(��) �����ƍl���Ă�������
��ɂ��Ă����������ׂ��ė�����
�����ė�����
�ǂ��܂ł�������
�����ȉ��Ƌ���
�Èł̒��ɔg�䂪�L������
�����ɂ͌���������
�^���Âʼn��������Ȃ�����
�g��͏������Ȃ���
���̂���������
�����ɂ͌����������
���͂������������Ȃ�����
�����Ȑ����̗]�C������
�܂��킸���ɋ�C��h�炵�Ă���悤��
�����ɂ͌�����������
���łɂ����Í��ƐÎ₵���Ȃ������
���̒��ɗ���������
������܂ł��ǂ蒅�����낤��
���F�̔g��
������
����͎����g�ł���̂�
�z�Ƃ��Ď�������Ȃ�
�����ĉ���������
�Ăю��͖Y��Ă��܂�
�̑��݂�����
���̂Ȃ�
�Y�ꂽ������
9/9(��) Syd Barret
 |
���̃T�C�g�̃l�[�~���O�Ɋւ��̂���PINK FROYD�Ƃ����o���h�ɁA�����̍��̃��[�_�[�ł�������Syd
Barret(�V�h�E�o���b�g)�Ƃ����M�^���X�g�������B
�ނ́APINK FROYD�̋ȍ���S�����A�o���h�̃{�[�J���X�g�ł����������A�t�@�[�X�g�A���o�������[�X�̌゠���肩��A���_�Ɉُ�𗈂��h���b�O�ɂ͂܂��Ă����B
�����Ď��H�A�E�ށB���̌�A�\���A���o�����o�����A����Ȍ�̔ނ͉��y�̐��E�Ɏp�������Ȃ��Ȃ�B
�ނ�"�������_�C�������h"�ƌĂꂽ�B |
| �����A�l�b�g�ł��܂��ܔނ̊G�ɏo������B |
 |
����͎��������������̊G�̈�B
���ꂵ���Ȃ�悤�Ȃ����������E�ɋz�����Ă��܂��̂́A�������甭�����Ȃ��̋��|�Ɉ��������邩�炾�낤�Ǝv���B
���X�A���肱�݂����ɂȂ鋰�낵���ǓƂ�����B
�ƂĂ������ł��ł��Ȃ��A�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ����̂�����A�Ƃ肠�������͌����Ȃ��Ƃ���ɒǂ�����Ă��܂��B
�����邱�Ƃ����Ȃ�Ȃ����A�ǂ��������ėǂ��̂����������Ȃ��B
�̂��ł����Ă����Ɗ����Ă��Ă��A�����Ƃ��߂������Ƃ��o���Ȃ��B
����ǁA�ǂ���邱�Ƃ��o���Ȃ��قǂɋ߂Â��Ă�����A���ɕ����킳���Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ��L��c�B
���̎����́A���̋��|�̉��̒��Ɏ���������肱��ōs���̂�������Ȃ��B
�O���猩�鋰�|�͊������Ȃ��B
���|�ɂ����ۂ�����ꂽ��A�����͏����͒g�����낤���B
���ꂪ�A�V�h���������E�Ȃ낤���B
|
9/2(��) �u�łɂȂ�e�v
�@�Ƃ����V���b�L���O�ȃ^�C�g���̖{��ǂ��ƁA���������Ղ����Ղ������Ă��܂����B
�ȂA��e�ɂ��肩�܂��Ă��āA�Y��Ă����B
�����Ɩ��R�ς݂����m��Ȃ����e�Ƃ̊W���B
����ꂱ�ꂩ��܂��A��d���c���Ă�̂��B
�����������Ȃ�Ƃ��ЂÂ���A���͎Љ�Ƃ̊ւ��̒��ŁA�����Ɗy�ɂȂ��͂����B
���ɂ́A���܂�ɖ�����ł����܂ŗ�������A�{�邱�Ƃ��Y��Ă����B
�q�ϓI�ɓ{��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł���̂͊m���Ȃ̂ɁA�قƂ�Ǔ{�肪�N���Ă��Ȃ��̂́A�����������炻���S����e�ɂ���ւ��Ă������炾�낤�B
���Ɂw�I��Ȃ������x��ɁA���Ɂw�I��Ȃ������x�����ɁA�{��̖���������Ă��܂�����������Ȃ��B
���́A����{�����肷�邱�Ƃ�����邽�߂ɁA������c�Ȃ��Ă����悤���B
�@����Ȃ��Ƃ��l���Ă�����A�Ȃ�����قǕ���������������̖��_�o�����A�����������ǁA�����̂悤�Ȗ��C���ɕϊ�����n�߂��B
����Ɠ����ɁA���́A���̕��ɂ��ĉ����m��Ȃ��Ƃ������ƂɁA�C�Â��ċ������B
�@���āA�u�łɂȂ�e�v�̍Ō�̒P���ł́A�w�e�Ƃ̑Ό��x�����邱�Ƃ����߂Ă���B
�Ȃɂ��A���������������Č��������̂ł͂Ȃ��B
�ނ��낻�̋t�ɁA����I�ɂȂ炸�ɁA��ÂɁA�����̃p�^�[���Őe�̌��t�ɗ��ߎ���邱�ƂȂ��A�����̐^�̎v����`����̂��B
�^�̎����̃Z�����j�[���B
�@���̂悤�Ɏ���ł��܂������ɂ͂ǂ��Ό���������̂��c�Ƃ����ƁA�莆�������ēǂݏグ��̂��������B
���̎ʐ^�Ƃ��A���ɋ߂����l�Ƃ��A�Ƃɂ������ɂƂ��Ă̕��e�̃V���{���̂悤�ȉ����̑O�ŁB
���̂����A����Ă݂悤�B
���������������̂��A�����Ȃ��牽������̂��A�|���āA�����Ċy���݂��B
�����o���͂���Ȃӂ����ȁB
�w���́A���Ȃ��̂��Ƃ��ǂ��킩��܂���B�x
�{���ɁA�킩��Ȃ����Ƃ��炯���B
�{���ɁA���͂��̐l�̂��Ƃ������m��Ȃ��B
�����A�����D���Ȃ̂ɁB
8/20(��) ��l�ŗ��Ƃ�������
�@�@�`�œf���o�[�W�����Ȃ̂ŁA�T�C���̕��͓ǂ܂Ȃ��ł�
�@�v���Ԃ�ɋ��F�Ɖ�������Ƃ����������ŁA�F��Ȏ����l���Ă���B
���~�x�݂ɓ��鏭���O�̂��Ƃ��B
�@
�@���́A�C���������炮��Ɨh��Ă��鎞���������B
�ڂ����J���Ă����Ɛ^�������悤�Ƃ����̂͂�������ǁA���̎������̌��Ă��܂������̂ɏ����Q�ĂĂ��B
��u�������悤�ȋC���������̌��i�́A���ɂƂ��ăJ���X�}���������́A�^���́A����̂܂܂́A���g��́A�����̒j�Ƃ��Ă̎p�������B
�������Ԃ������āA����ƌ�����悤�ɂȂ������i�������B
�@���N�Ԃ��K�q�͉����ς���Ă��Ȃ��āA���ς�炸�����̑��ŁA��n�ɂ�������Ɠ����ė����Ă����B
�����ڂ͂ӂ�ӂ�ƕY���Ă���悤�ł��āA����ǁA�������Ɖ����Ă��r�N�Ƃ����Ȃ��B
����ȂƂ��낪�ȑO�̂܂܂������B
�Ɛg�ŁA���C�y�Ɋy�����i���Ă���ޏ��́A���̉Ƃ̒���������ƌ��Ă����������B
�u��l�������Ȃ����ǁA�������Č���Ɠ�l�̐�����������Ƃ����܂����˂��B�v
���������Ȃ�����A�ޏ��̎��M�ɖ������p�́A���X�Ƃ��Ă����B
�@���̓�����A������Ƃ��l���Ă���B
��l�ŗ��Ƃ������Ƃ��B
�u�l�v�Ƃ��������̌`�̂悤�ɁA�l�͈�l�ł͐����Ă����Ȃ��B
�c�Ƃ����A�b������B
�x�������āA���Y���Đ�����̂��ƁB
����ɂ��Ă͈٘_�͂Ȃ��B
�l����l�ł͐����Ă����Ȃ����ƁA���������A�x������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A�ɂ��قlj����Ă���B
�����ǁA�u�l�v�Ƃ����������A���ɂ͋��ˑ��́A�����Ȃ��͂Ŕ��荇�������݂���������l�̌`�ɂ�������B
�������l�ŗ��Ƃ��Ƃ���ƁA����͓|��Ă��܂��B
������A���������܂��Ƃ����݂��A��肩���点��B
�����Ƃ��Ƃ��鑫��K���ň�������B
��������
�u���܂ŁA����ʓ|�����Ă�����̂ɁB�v
�u���Ȃ��̂��߂ɐl����_�ɐU���Ă����̂ɁB�v
�u�����Ǝ����̂��Ƃ͓�̎��ŋ]���ɂȂ��Ă����̂ɁB�v
��������A���Ȃ�B
�u�l�v�Ƃ��������̘b�́A���ˑ��卑���{�炵���A������Ɏg����֗��Șb�ɂ��Ȃ�B
�@K�q�́A�ȑO�������B
�u������Ȃ�? �D���Ȃ悤�ɂ��Ȃ�B���͉������Ă邩��B�v
�Ԃ�����ڂ��ɂ����������B
�u���肪�ƁB�v
������������Ƃ����������B
�@�ޏ��̉��l���A�ȑO�������Ɖ���悤�ɂȂ����������A������ƌւ炵���B
��l�ŗ����Ă����A��Ȑl�Ɗ��Y���ĕ�����B
�N�����炭�Ȃ������A�������蓥���āA����݂���B
�����Č��C�����߂��A�Ăѕ����o�������ɂ́A�K�����F��Ȃ��猩���B
�@��������Ȑl�ɂȂ肽���B
����ȕ�e�ł��肽���Ǝv���B
8/17(��) �Ƃ��Ă�������
���������킯�ŁA
�c�Ƃ��Ă�������

2�V���b�g
�����Ɗ�����
 �@ �@
3�V���b�g
�c�ł�(;_:)
8/12(��) ����������
�����@��N�������Ƃ��Ă�����̂��@
���Ȃ̂�����������
�́X�@�����Ɏ������߂����̂�
�������Ȃ������̂�
�N���Ɍ���ꂽ���Ȃ������̂�
���߂Ă��܂���
������@��N�����Ȃ�����
�����Ɓ@�@��o���Ă݂���
����قNj��낵���Ȃ�����
�v���Ă����قlj����Ȃ�����
��l�̎���������
�ĊO�����������̂���
���Ă݂悤
8/2(��) ������
�@�������Ƃ��鎄�̑��ɁA�����������������Ă�B
����Ȏ������ƁA�������������Ǝv����B
����͉����Ă�B
�ł��m���ɁA���ɉ������܂��Ă�B
�@�[�ׁA���������B
�v�̂��߂ɋ~�}�Ԃ��Ăڂ��Ɠd�b��������ƁA���̂��ꂪ�o�Ď��ɂ�߂��U�炵���B
���������Ă���̂�����Ȃ��B
����{���Ă���̂�����Ȃ��B
�v���悹�āA�Ԃ��o�����B
�^���ÂŁA���������Ȃ��B
�}���ł���̂ɁB
�����͏��w�����獂�Z���o��܂ŏZ��ł����X�̒ʂ肾�����B
��납��͒N����2�l�ǂ������Ă���B
�����邯�ǁA�����Ԃɍ���Ȃ��B
�ǂ������B
�����̋��ѐ��Ŗڂ��o�߂��B
���͉����A�Ƃ�ł��Ȃ����̂��@��N�������Ƃ��Ă���̂����m��Ȃ��B
����ǁA���܂����n���ɋ����ĕ�炷���A�댯���������Ăł�������������Ă��܂�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
8/1(��) �l�����y����
�@���܂ŗ����ł��Ȃ��������X�̂��Ƃ��A���E���J����悤�ɂς����ƌ������C�������B
�����Ɖ���Ȃ��������̓����͊ȒP�Ȉꌾ�������B
�u�l�����y���ށv
�@�ƂĂ��y�������Ȓʂ�́A�������������B
�܂�������͉���Ȃ����ǁA���̒ʂ肪�ǂ��ɂ���̂����������B
�����ɂ́A���܂Ŏ��������ł��Ȃ��Ǝv���Ă����l�X�������Ă���B
���������A���̒ʂ����������B
�@�������g���y���܂��邽�߁c�������y�����Ǝv�����Ƃ���邽�߂Ɍ��ʂ��C�ɂ����ɏ����Ɋ撣�鎖�́AOK�Ȃ̂��B
����́A���N�I�Ɏ����������邱�Ƃ��B
�����āA�y�����A�撣���Ă���ƁA�咣�ł��邱�Ƃ��B
���͎�����N���������Ă���̂ŁA�����]�ނ��Ƃ����āA�����y���ނ��߂ɓw�͂���B
����́A�N���̂��߂ɂ�邱�Ƃ���Ȃ��B
�N���̍����]���邽�߂���Ȃ��B
�����̌��ʂ��A���҂���N���ɍ����o�����߂���Ȃ��B
���ꂪ�A�N���������邱�ƂɂȂ�͂����Ȃ��B
�����āA�����悤�Ɉ�����l���l�����y���ނ��߂ɂ��Ă���w�͂�����邱�Ƃ��o����̂́A�f���炵�����Ƃ��B
��������Ĕ��R�ƕs���ɂȂ�����A��������A�W�Q�����肷�邱�Ƃ̂ق����A�����ƕa��ł���B
�����A�y�������́A�y����������Ă����B
�y�������āA�����Ă�����B
�y��������B
7/31(�y) �K�ȁE�ȁEhabit
�@ Portia Nelson�̎��̒��ɂ��ADave Pelzer�̒����̒��ɂ�����A��(�K��)�Ƃ������t���C�ɂ������Ă����B
�@Portia Nelson�̎��ɂ́A�V�̒i���ɏo�Ă���B(�G�L 7/8)
���͑����A�����̒i�K�ɂ���B
���͌����Ă��邯�ǁA����ł������Ă��܂��B
���ꂪ�K��(����)���ƌ������Ƃ������Ă��āA�ڂ͊J���Ă��āA�l�̂�������Ȃ��A�����̂������ƂȂ̂��ƋC�Â����Ƃ��o����B
������������o��B
���͑����c�����܂ł͗���ꂽ�悤�Ɏv���B
���̎��̌������l�b�g�Ō����܂����B
III.�@I walk down the same street.
�@�@�@There is a deep hole in the sidewalk.
�@�@�@I see it is there.
�@�@�@I still fall in....it's a habit.
�@�@�@My eyes are open.
�@�@�@I know where I am.
�@�@�@It is my fault.
�@�@�@I get out immediately.
�@�w���邭�l����u�N�Z�v�����悤�x
�����Dave Pelzer�̌��t�B
���̖{�̏Љ�Ŏ����ŏ��������͂ɁA�����?�Ǝv�����B
�w�����Ƀ}�C�i�X�̔��������Ă��܂������ɋꂵ��ł����ߋ�������Ȃ�A���̂�������ȁu�N�Z�v�����ꂩ��͖����ɂ��Ă��܂��Ƃ����͋��������҂炵�����z���Ǝv���܂��B�x
�@�����Ǝ��́A�\�̓��L���������Ƃŋ��R�Ɂw���邭�l����N�Z�x�����n�߂Ă��邩���m��Ȃ��B
������Ԋy�����������Ƃ́A��Ԃ������납�������Ƃ́A��ԐS�Ɏc�������Ƃ́c�Ƃ����l����B
���R�ƕ`�������G��������ł���B
�`���Ȃ���A�����S�̒��ɂ���w�y�������̈����o���x�ɓ����B
���́w�y�������̈����o���x�̒��g�́A�����������Ă����B
���������o�������A�`�����Ŋy�������Ȃ�B
�ǂ����Ă��y�����Ȃ�Ȃ��������āA����Ȏ������q�ϓI�ɕ`������A�Ȃ��������������B
����ȃN�Z�̂��������A��̕��@�Ȃ̂����m��Ȃ��B
����Ɠ����i�s�ŁA��������Ă��̏ꏊ�œ��̐��������Ă���B
�\��������Ȃ����Ƃ������ɏ����B
�����獡���ς�炸�A�����͕\�������Ђ�����߂āA�������莄���g�̕��g�ɂȂ��Ă���
������Ƒ傰�������ǁA�����ɁA���̌��_�ƒ����A�܂Â��Ɛ����A�コ�Ƌ����A�Â��Ɩ��邳�A�s���Ɗ�]������B
7/23(��) �ǂ������ł���
�@�����̃j���[�X�ő]��ЂƂ݂����삳���l�ƐV�h�䉑�����U�����Ă���Ƃ��낪�f���Ă��܂����ˁB
���ƈꏏ�ɂ��Ă͎���ł����A�ȑO����]�䂳��ƁA�����̎��������d�Ȃ��Ă��܂��A�����ƕ��C�ɂ��Ă����̂ŁA�ƂĂ��������Ȃ�܂����B
���삳��Ɗ�������킹�Ĕ��ݍ����p�ɂ́A��������`��Ƃ��Ă��܂��܂����B
��u���ꂳ��̈���ɕs������������Ƃ��������̂����m��Ȃ�����ǁA�����̂��삳��B�̏Ί�͂ƂĂ��f�G�ň��炩�������悤�Ɏv���܂����B
�����A���͖��Ɣ��ݍ������Ƃ��o���܂��B
�{���ɗǂ������B
7/18(��) ����
���͂�N������ł͂��Ȃ��̂�
�ǂ��ɂ����ӂ͖����̂�
�������ɂ��邾���Ł@
�������ǂ�ǂ����Ȃ��Ă����̂�������
�ǂ�ǂ���Ȃ����݂ɂȂ��ā@
�������肻���ɂȂ�
���X�ƐU�镑���Ă݂邯��ǁ@
��������Ă��鎩����
�u���܂��A���ȃ��c����v
�Ɨ₽�������𑗂��Ă���
����́@�����Ƃ����������Ƃ������Ă����Ӓn���Ȏ�����
�����ʂꂽ�Ǝv���Ă���������
�܂������̂��@
�܂��Ђ���ł��̂�
�܂��@����
����ł�������
���̂��Ƃ͒m���Ă�
�ǂ��m���Ă����
�����ǂ����@�x�z�͂���Ȃ�
�@
7/8(��) �T�̒Z���͂���Ȃ鎩���`
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�`Portia Nelson
�T .���͒ʂ������B
�@�@�[����������B�@
�@�@���͗���������B
�@�@���͂ǂ������炢���̂�������Ȃ��A�E�E�E�ǂ����悤���Ȃ��A
�@�@����͎��̊ԈႢ����Ȃ��B
�@�@�o����������܂ŁA���̂��������Ԃ�������B
�U. ���͓����ʂ������B
�@�@�����ɐ[����������B
�@�@���͂�������Ȃ��ӂ�����āA�܂��܂�����������B
�@�@�܂������ꏊ�ɂ���̂��M�����Ȃ��B
�@�@�ł��A����͎��̊ԈႢ����Ȃ��B
�@�@��͂�o��̂ɂ����ԂԂ�������B
�V. ���͓����ʂ������B
�@�@�����ɐ[����������B
�@�@���ꂪ����̂�������@�@�@�@�@ �@�@�@
�@�@����ł����͗���������A�E�E�E����͏K��(����)��
�@�@���̖ڂ͊J���Ă���B�������ǂ��ɂ���̂�������B
�@�@����͎��̂������Ƃ��B
�@�@������������o��B
�W. ���͓����ʂ������B
�@�@�����ɐ[����������B
�@�@���͂��������ĂƂ���B
�X. ���͕ʂ̒ʂ������B
�@�ȑO�A�\�̓��L�ň��p�������Ƃ̂��邱��Portia Nelson�̎����A�Ăюv���o���悤�ȏo�������������B
�ς�肽���A�����Ɗy�ɐ��������Ɯf�r���Ȃ���A�C�Â��Ƃ����������̒ʂ������Ă���B
�����ē������ɂ܂������āA�Ȃ�Ŏ��ɂ��肱��ȕs�K�����x���N����̂��Ɓc�ƒQ���Ȃ��甇���オ��B
����ǂ܂��f�r���A�܂������ʂ�ɖ߂�A�������̑O�ɗ����c�B
�J��Ԃ��������ɗ�����p�́A���l���猩��Ί��m�Ȃقǖ��炩�ȊԈႢ�ł����Ă��A�����҂ɂƂ��Ă͕K���Ɋ撣���Ă���̂ɂ܂������Ă��܂��������Ȃ����Ȃ̂��B
���́A�����͂܂������ɂ���̂��낤�B���̐[�����̒��ɁB
��������́A�̋����ꏊ�����炶��Ȃ����낤���B
��ԑ����̎����߂������A���Ă̋��ꏊ����������B
�������ǂ�Ȃɋꂵ���ꏊ�ł���A���x�����ӎ��ɖ߂��Ă��܂��̂́A���̐[�����̒��ł�����蒼���������Ȃ��悤�Ȏv�����݂�������Ȃ��B
�ڂ��J���āA�����ɈÂ������J���Ă��邱�Ƃ�����̂́A�E�C������B
����ǁA���Ȃ���܂�������B
�����Ă��܂��̂́A���ǎ����̈ӎu�Ȃ̂��B
����ɋC�Â����Ƃ́A�����邱�Ƃ�肸���Ɠ���āA�|���B
�@�^�ɕς�肽���Ɗ�����Ƃ��A�����ƕω��̃`�����X������B
����ǁA�ω��ɂ͒ɂ݂������A�{���͂��ꂪ�|������A���ɋC�Â��Ȃ��ӂ�����ė�����̂��낤�B
�`�����X�͂܂�����B�����҂ɂƂ��Ắu��Ɂv�Ƃ����`�ŁB���x�ł��B
�ڂ����J�����ӂ́A����Ǔ����҂ɂ����ł��Ȃ��B
���̒ʂ肩��Ă�Ă��A���̒�����A�u���܂��̂����Ł`�v�Ɣl���Ă��A���������ɂ͍s���Ȃ��B
�������͊��ꂽ�ꏊ�����ǁA�����čK���ȏꏊ����Ȃ��B
���邢������Ȃ��B
�����������Ă���ꏊ������B
�����Ɩ��邢�ʂ肪�A���ɂ���������B
�������g��I�ɏグ�āA�l�ɕω���������͈̂Ӗ����Ȃ��B
����낤�A�҂Ƃ��A�F�낤�B
����Ȏ��A�������鎖�������B��ōō��̃��b�Z�[�W���B
�������Ďv���o���B
�������̒����狩��ł������ɁA�ʂ̒ʂ肩��F���Ă��Ă��ꂽ�l�����̂��ƁB
���̐l�����̌��t���A�܂�ŊO����̂悤�ɗ����ł��Ȃ����������̂��ƁB
�����ƍ����A�����Ƃ����Ɩ��邢�ʂ肩��A�������ċF���Ă���Ă���l������̂��낤�B
�����Ƃ����Ǝ��R�ōK���ȏꏊ����B
�@�@
The Portia Nelson Home Page
7/1(��)�@�u�Ƒ����v�@2
�@�������Ȃт�����A�u�Ƒ����v��Ǘ��B
���̏��q���Z���́A�O�֑O�������đ傫������B
�ޏ��������������̂́A�ޏ��̎���́c����͔ޏ����w�̖͂��Ɏ�ɓ���Ă��������̂悤�Ȃ��̂������̂�����ǁA�����Ď����ЂƂ�̗͂���Ȃ������B
�o��Ƃ��A���Ƃ��A�G�ꍇ���Ƃ��A�l�Ɛl�Ƃ̊ւ���\�����t�͂ǂ�������݂Ɏv����B�����ǁA�l�Ɛl�Ƃ��{�C�ŐS���J���Ċւ�鎞�A�����ɐ��܂�o��G�l���M�[�͊�ՓI�ȑ傫���ɂȂ�\�����߂Ă���B
�@��҂ł���V���r�������"���Ƃ���"����B
*****
���E�ɂ͂��܂��ߌ������ӂ�Ă��܂��B�����ɂ��A�����ȉƒ�̂Ȃ��ɂ��A�炢�o�����������̂悤�ɋN���Ă��܂��B�����ƂЂƂ�ł͖����ł��B�N���Ɛ������������A�x������Ȃ��ƁA�ꂵ�����܂��B�E�C�������āA������ݏo���A����������c�c���ꂾ���ŁA�ӊO�ɑ傫���ω���������悤�Ɏv���܂��B
*****
�@���ꂩ��ǂ܂��������������邩���m��Ȃ��̂ŁA���炷���ɂ��Đ[���͐G��Ȃ����A�w���B�͂��ꂩ��A�u�Ƒ��v���ǂ����Ă������炢���낤�B�x�����������b�Z�[�W������ɗ���Ă��鏬���������B
�o�ꂷ��l�X�͊F�A�Љ�̒��ʼnߋ�������Đ����Ȃ���A�Ƒ��ɂ�����l�X�ȔY�݂��������Ă���B
���ƒ������˂���ċN����A����ƎS�E�����B
��������ɁA���������X�ɑ{������Y���A�S��a���̍ȁA���p���t�A�����q�̏����A�������k���̎Ⴂ�E���A���q�ƒ�̃A�����̕��e�A�{�݂ŕ�炷���̗c�����A���q���s�҂��ĕ��������j�c���ꂼ�ꂪ�{�����݂�ǓƂ���߂����Ă��܂��Ȃ���A�������Ă����B
�ޓ��̌����́A�V��������ݏo�����҂ƁA�j�ł��ނ������҂Ƃɑ傫��������ꂽ�B
�����Ă��̌���I�ȍ��́A�^���Ɋւ�낤�Ǝ�������ׂ̂鑼�҂ɋC�Â��A���̐l�ɐS���J�����Ƃ��o�������ǂ����c�ł������悤�Ɏv���B
�����̒��ł��A�Љ�͕s���������A�ǂ̓o��l���ɂ��A�K�������ȃ`�����X��A�~���ƂȂ�o����������B
�����A������C�Â��Ȃ��قǂɋ��܂��Ă��܂����S�́A�ǂ�����~��ꂽ�̂��B
�ł̒�����o�Ă���̂����ݑ������ޓ��́A�ǂ�����ΐV������������ݏo�����̂��B
����I�ȉ������@�ȂǁA�����Ɩ����낤�B
��͂�A�u�N���Ɛ������������A�x�������A�E�C�������Ĉ�����ݏo���c�c�v�ƁA��҂̂��Ƃ����ɏ����ꂽ�n���ō��C�̂�����@�̒��ɂ����A�o������������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
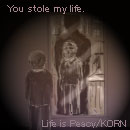
before
|